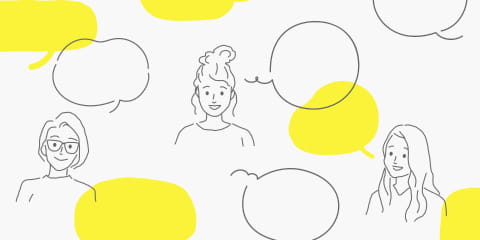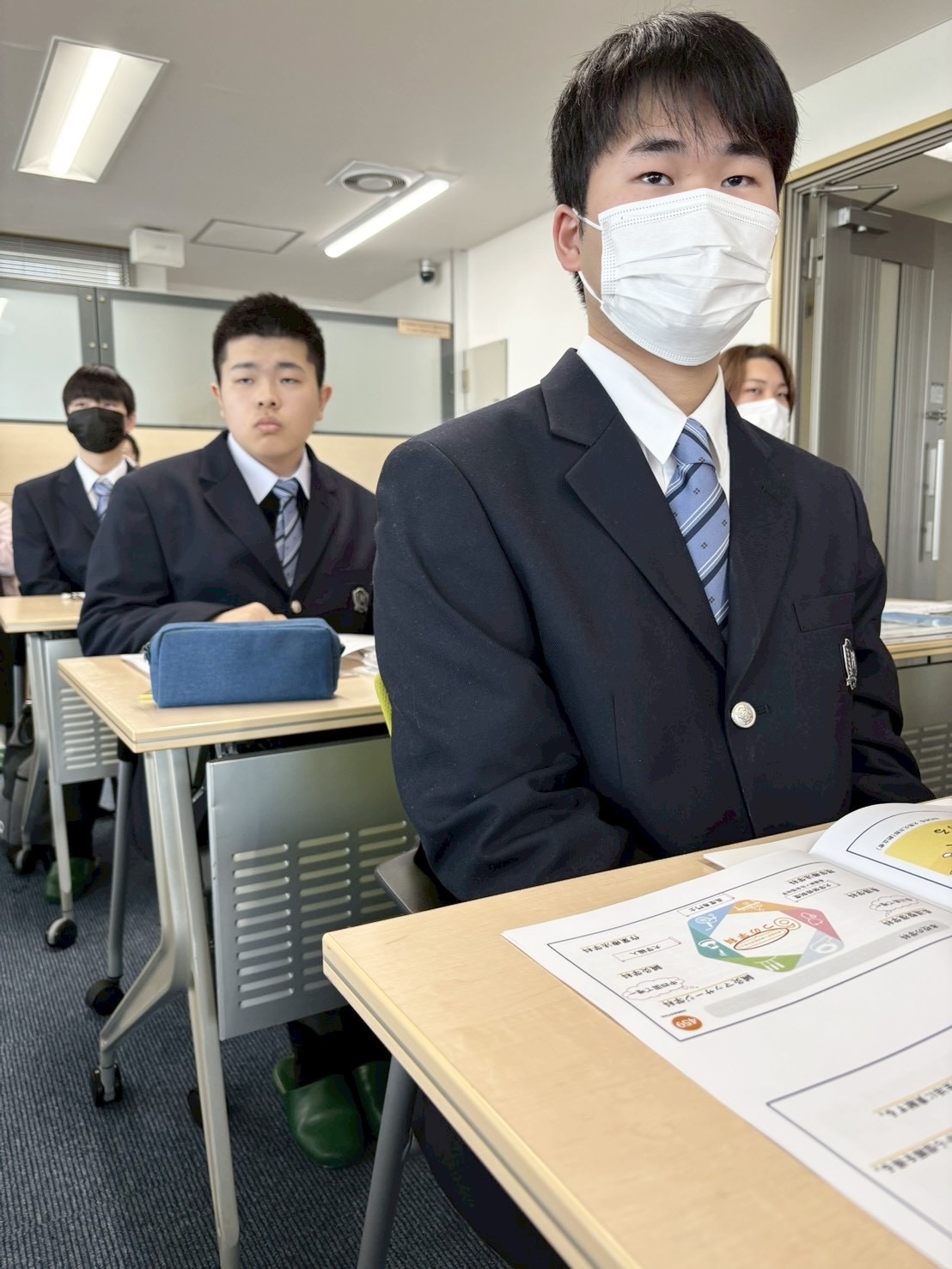心理士カウンセラーのブログ
Psychological counselor Weblog
【発達障がい・不登校でも安心!ウィスク検査の結果を「強み」に変える進学ガイド】
2025.04.03
4月になりました。
中学3年生のお子さんはいよいよ受験生となります。
今回は、発達障がいの疑いがあるお子さんや
不登校傾向の状態にあるお子さんの
進学をお考えの親御さんに向けて、
WISC(ウィスク)検査の活用と、そこで得られた結果を
「強み」へと変える方法についてご紹介します。
「子どもに発達障がいの可能性がある」
「不登校が続いていて、全日制の高校に通えるか不安」
という親御さんが増えている昨今です。
しかし、通信制高校という選択肢をうまく活用すると、
お子さんの個性やペースに合わせた学びが可能になります。
ここでは、WISC(ウィスク)検査とは何か、
検査結果から得られるヒント、
そして当校で実践している学習サポートの具体例をお伝えしながら、
「高校卒業」までの道のりを
より明確にイメージしていただくためのガイドをお届けします。

《WISC(ウィスク)検査とは? どんなことが分かるの?》
WISC(ウィスク)検査とは、
主に5歳0か月から16歳11か月までの
お子さんを対象とした知能検査の一種で、
認知能力の偏りや得意・不得意の分野を
把握する目的で実施されます。
正式名称は「Wechsler Intelligence Scale for Children(ウエクスラー式知能検査)」で、
日本では最新の第5版(WISC-Ⅴ)が広く利用されています。
WISC検査では、一連の下位検査を通じて
以下の5つの指標(合成得点)を測定し、それらを総合的に解釈します。
VCI(言語理解指標)
・語彙力や言語表現力、概念理解の力を測定する
VSI(視覚空間指標)
・目で見た情報を処理し、空間を把握する力を測定する
FRI(流動推理指標)
・図やパターンの規則性を見つけ、論理的に考える力を測定する
WMI(ワーキングメモリ指標)
・一時的に情報を記憶しつつ作業を進める力を測定する
PSI(処理速度指標)
・視覚情報をどれだけ素早く正確に扱えるか、作業のスピードを測定する
これらの結果を踏まえると、
「言語的なタスクが得意だけれど、作業速度が遅い」とか、
「視覚的な情報処理は強いが、ワーキングメモリが弱いため
複雑な指示を同時にこなすのが苦手」
といった個々の特徴が明確になります。
特に発達障がいや不登校の背景には、
このような認知の凸凹が潜んでいることが多く、
WISC検査がその理解を深める大きな手がかりとなります。

《発達障がい・不登校の子がWISC検査を受けるメリット》
1) 得意・不得意を客観的に把握できる
発達障がいや不登校の子は、自分で
「なぜ学校に行けないのか」
「どうして特定の教科だけ苦手なのか」
を言葉にしにくいことがあります。
しかし、WISC検査のデータがあると、
「実は視覚的な情報処理が得意」
「作業に時間がかかるのは処理速度が低めだから」
といった具体的な理由が分かり、
本人・家族ともに納得しやすくなります。
2) 自己肯定感を高めるヒントになる
不登校の子や発達障害のある子は、
「周りと同じようにできない自分」を責めてしまいがちです。
しかし、WISC検査の結果から
「実はこんな強みを持っている」
とポジティブに見いだせれば、
「自分だって得意なことがある!」
と自信を持つきっかけに変えられます。
3) 適切な学習環境・進路選択につながる
学校生活の中でうまくいかなかった背景が、
WISC検査によってクリアになることがあります。
そこで、
「自分の特性に合った学校はどこか?」
「どんなサポートが必要か?」
を具体的に考えられるようになるため、
通信制高校などの柔軟な学習スタイルへの進学が検討しやすくなります。
《WISC検査の結果を『強み』に変えるための3ステップ》
WISC検査を受けるだけでは、残念ながら意味がありません。
大切なのは、検査結果をどのように活かすかです。
ここでは、「結果を強みに変える」ための
3ステップをご紹介します。
ステップ1:検査結果を正しく理解する
WISC検査の報告書には、
得点や指標の解説が書かれています。
しかし、用語が難しく感じることも多いですよね。
その場合は、検査を実施した専門家(心理士や医師など)に
しっかり説明を受けましょう。
「VCIが高いとは具体的にどういうこと?」、
「処理速度が低い場合、日常でどんな困りごとが起きやすい?」など、
疑問点を遠慮なく質問してクリアにすることが大切です。
ステップ2:家庭や学校での具体的サポートを検討
たとえば、「処理速度が低い」という結果が出た場合、
テスト時間や宿題の締め切りを少し長めに設定するだけでも、
お子さんの負担は大きく減る可能性があります。
視覚的な認知が得意な子なら、
授業ノートをイラストや図解でまとめる習慣をつけることで、
覚えやすさが格段に向上します。
こういった「学習支援」や「環境調整」は、
家族が工夫するだけでなく、
学校にも伝えて協力してもらうことが重要です。
不登校傾向がある場合でも、
通信制高校などでは学習ペースや通学頻度を
柔軟に設定できますので、
WISC検査の結果を活かしたプランを一緒に立てることができます。
ステップ3:本人が納得し、自己肯定感を育む
WISC検査の結果は、
「本人にどのように伝わるか」が非常に大きなポイントです。
親や教師がサポート策を提案する際も、
「あなたは○○が苦手だからこうしなさい」という言い方ではなく、
「○○が得意だから、こんな勉強法を試してみよう」
「××が苦手とわかったから、解決策を一緒に考えよう」
とポジティブなアプローチを心掛けることが大切です。
本人が自分の特性を否定するのではなく、
「自分にはこういう個性がある」と受け止めて前向きに活かせるよう、
声をかけてあげましょう。
通信制高校だからできる! 個性に合わせたサポート事例
通信制高校の最大の特徴は、学習スタイルの柔軟さにあります。
全日制の学校のように朝から夕方まで毎日通学するのではなく、
週1日から5日までの登校日数を選べたり、
在宅学習をメインに据えたりできるのです。
(事例)自己主張が苦手な不登校生へのメンタルサポート
WISC検査で判明:
言語理解は平均的だが、処理速度が低め。
対人関係のトラブルから不登校になり、自分の気持ちを伝えるのが苦手。
サポート策:
学校のカウンセラーと定期的に面談を実施し、
授業は在宅メイン+週1日の登校で友達との接点を少しずつ増やす。
授業中の発表や課題の共有も無理強いせず、
本人が安心できる方法(チャットやメール)を使って提出を進める。

《学校選びのポイント:WISC検査を活かすために大切なこと》
「通信制高校」とひと口に言っても、
そのシステムやサポート体制は学校ごとに大きく異なります。
WISC検査の結果を上手に活かすためには、
以下のポイントを意識した学校選びがおすすめです。
●個別サポートが充実しているか
学習指導だけでなく、カウンセリングや発達障害に関する
知識を持ったスタッフがいるかどうかは重要です。
少人数制のクラスや、コーチングに力を入れている学校は、
親御さんとの連携もしやすくなります。
●柔軟な時間割や通学頻度を選べるか
朝が苦手なお子さんなら、
午後から通学できるコースがあるのか、
オンライン学習を中心に進めるプランがあるのかなど、
自分のリズムに合った学習方法を用意しているか確認してみましょう。
●ICT(情報通信技術)を活かした学習ができるか
タブレットやPCで教材を見たり、
動画授業を使ったりすることで、
視覚的理解が強みのお子さんをサポートできる場合があります。
学校によってはオンライン授業を実施しており、
自宅でもわかりやすい教材が利用可能です。
●在校生や卒業生の事例をチェックする
学校のパンフレットやホームページには、
在校生や卒業生の声が載っていることが多いです。
「同じように発達障がいや不登校で悩んでいたけれど、
ここで乗り越えられた」という事例を見つけると、
入学後のイメージが掴みやすくなります。
《当校の取り組み:学びやすさと安心を両立する仕組み》
当校では、発達障がいや不登校を抱える
生徒の特性をしっかりと理解した上で、
それぞれの生徒が持つ「強み」を伸ばせるような体制を整えています。
具体的には:
●専門スタッフによるWISC検査の解説と面談
希望される方には、WISC検査の結果を専門スタッフがわかりやすく解説。
保護者の方と一緒に、学習面や生活面で気をつけるべきポイントを相談します。
●個別学習コーチング
毎月のコーチング面談で「今月の学習目標」や「得意分野を活かす課題の設定」を行い、
定期的にフィードバック。苦手分野に対しても対策を講じやすくなっています。
●柔軟な登校スタイル
週1回、3回、5回など、通学回数は
ライフスタイルや体調に合わせて選べます。
オンライン授業も並行して活用できるので、
在宅学習と通学を無理なく両立できます。
●カウンセリングルームの常設
不登校や対人関係の悩みを抱える子がいつでも相談できるよう、
カウンセリングルームを常設しています。
必要に応じて保護者との面談も行い、
家庭と学校が連携してお子さんを支えます。

《卒業後の進路イメージ:通信制高校で育むチカラ》
「通信制高校」と聞くと、「その後、進学や就職は大丈夫?」
と不安に感じる保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、通信制高校を卒業した生徒の多くが、
大学や専門学校、就職など多彩な進路で活躍しています。
1) 大学進学への道
WISC検査で見えた得意分野をさらに伸ばし、
高等教育の場で研究を深める生徒さんも少なくありません。
通信制高校在学中に得意科目の学習を深掘りすることで、
特定分野への興味関心を高め、志望大学を明確にするケースもあります。
2) 専門学校や職業訓練
ファッションやIT、介護、美容などの
専門学校へ進学する生徒もいます。
WISCの結果を踏まえて「自分の適性に合った分野」を選びやすくなるので、
将来の職業選択においても失敗しにくいという利点があります。
3) 就職・起業という選択肢
処理速度が遅いからといって
社会で活躍できないわけではありません。
むしろ、言語理解や発想力など「他の強み」を活かせる職場を選べば
大きく成長できますし、
在学中にプログラミングやデザインを学んで
フリーランスの道を目指す生徒もいます。
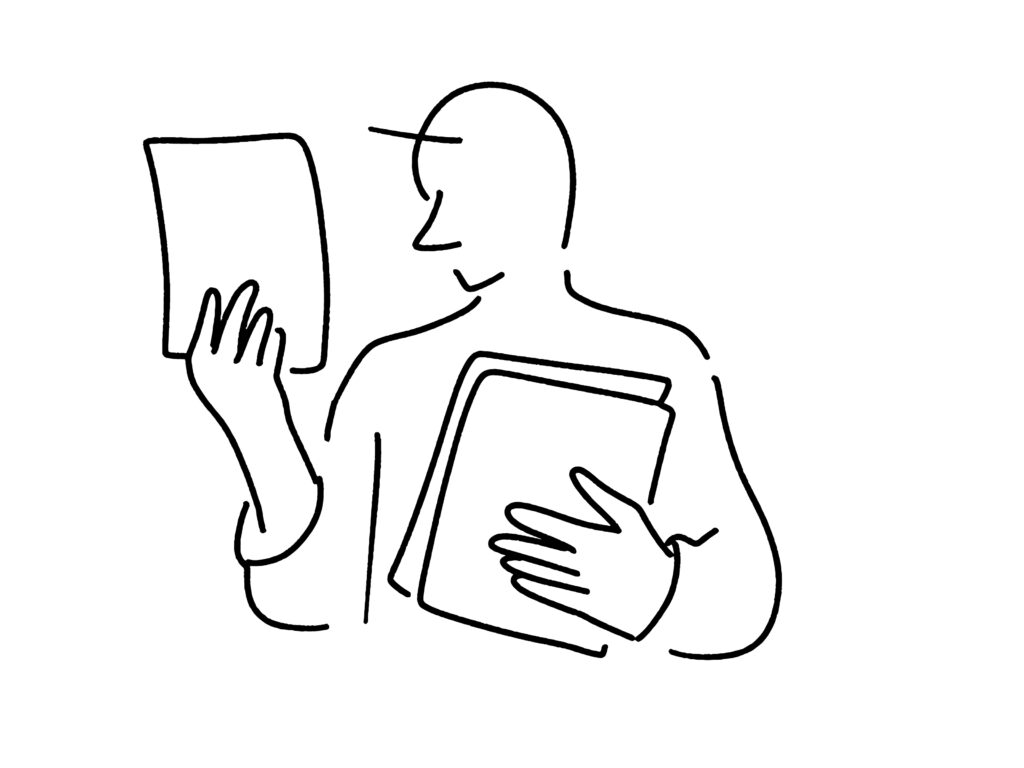
《WISC検査を活用し、お子さんの未来を切り拓こう》
発達障がいや不登校に悩むお子さんの進路選びは、
「周りと同じようにしなければ」
というプレッシャーを強く感じがちです。
しかし、実際には「特性に合わせた教育環境を選ぶこと」
が何より大切です。
そしてそのための第一歩として、WISC(ウィスク)検査が大変有効なツールとなります。
当校では、発達障がいや不登校を抱える生徒さんが
安心して学べる環境づくりに力を入れ、
専門スタッフによるWISC検査のアドバイスや個別コーチングを通じて、
生徒一人ひとりの「強み」を引き出しています。
もしお子さんの進路についてお悩みでしたら、
ぜひ一度ご相談ください。
一緒にお子さんの未来の可能性を広げるお手伝いができれば幸いです。
不登校や発達障がいの特性があっても、
自分に合った学びの場であれば、
必ず「自分らしさ」を活かして輝くことができます。
WISC検査という客観的なデータを上手に取り入れて、
お子さんの個性を最大限に伸ばし、
一緒に「高校卒業」そしてその先の未来へと進む歩みを、
私たちと一緒にサポートしていきましょう。
《最後に…》
松陰高等学校 高松校・丸亀校では
WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査や
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査の結果を元に
お子さんにとっての
ベストな教育環境や指導方針を組み立てています。
また、ご希望の方は、松陰高等学校 高松校・丸亀校でも
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査を実施しています。
どんな子どもでも
さまざまな特性があります。
その特性は
子どもを苦しめるだけではなく
使い方を変えれば
大きな武器になるのです。
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査をもっと活かしたい方は
いつでもお気軽にご連絡ください。
お待ちしております。
また、WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査や
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査を
ご自身でとれるようになりたい先生は
WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査のとり方や
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査のとり方も
お教えしています。
その場合もお気軽にお問い合せください。
では。。。
松陰高等学校 高松校・丸亀校
☎087-813-3781
✉info@kagawa-mirai.jp