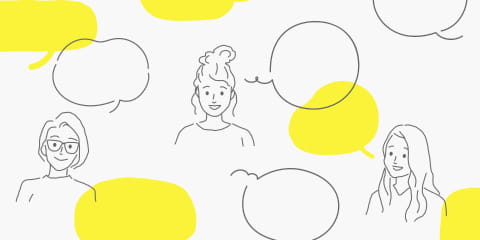心理士カウンセラーのブログ
Psychological counselor Weblog
【夏から始まる進路の準備~親子で考える進路選び:特性のある子の可能性を信じて】
2025.07.16
夏休みは、多くの生徒さんにとって心躍る時間ですが、
同時に、将来についてじっくりと考える
大切な時期でもあります。
特に、発達障がいや不登校、
HSC(Highly Sensitive Child)、不安障がいなど、
それぞれに異なる特性を持つ
お子さんを持つ保護者の皆様にとっては、
「うちの子の進路、どうしたらいいだろう?」と、
不安や疑問を感じることも少なくないのではないでしょうか。
「周りの子と同じように進路を決められるだろうか?」
「そもそも、どんな選択肢があるのだろう?」
「この子の特性を理解してくれる場所はあるのだろうか?」
そうしたお悩みを抱えるのは、
決してあなただけではありません。
松陰高等学校 高松校・丸亀校には、
様々な特性を持つお子さんがたくさん在籍しており、
私たち教職員も、日々、生徒さん一人ひとりの個性と向き合い、
その可能性を最大限に引き出すためのサポートをしています。
ここでは、夏休みという時間を活用して、
親子でじっくりと進路について考えるためのヒントや、
特性のあるお子さんの進路選択において
特に大切にしてほしいこと、
そして松陰高等学校がどのようなサポートを提供しているのかについて、
詳しくお伝えしていきます。
お子さんの「好き」や「得意」を大切にしながら、
自信を持って未来へ進むための一歩を、
この夏、一緒に踏み出してみませんか?

《【特性別】夏休み中に親子で取り組む進路準備のポイント》
お子さんの特性によって、進路準備の進め方は様々です。
ここでは、発達障がい、不登校、HSC、不安障がいといった特性別に、
夏休み中に親子で取り組んでいただきたい
進路準備のポイントをご紹介します。
1. 発達障がい(ADHD、ASDなど)のお子さんの場合
発達障がいのお子さんの進路選択では、
「得意なこと」を活かし、「苦手なこと」を補う視点が重要です。
具体的な特性の理解と可視化:
お子さんの発達特性を具体的に把握することが第一歩です。
「忘れ物が多い」「集中が続かない」
「特定の音に敏感」など、
日常生活でどのような困りごとがあるのか、
親子で話し合い、メモに書き出してみましょう。
同時に、「好きなこと」「得意なこと」も具体的に書き出してください。
「細かい作業が好き」「特定の分野に強い探求心がある」
「体を動かすのが得意」など、ポジティブな側面も明確にすることで、
将来の選択肢が広がります。
視覚的な情報が理解しやすいお子さんも多いため、
これらの情報を「特性マップ」や「得意・苦手リスト」
として作成すると良いでしょう。
職種や学びの場への興味を具体的に探る:
「将来何になりたい?」と漠然と聞くのではなく、
「どんな仕事に興味がある?」「どんなことを学んでみたい?」
と具体的に問いかけてみましょう。
興味のある分野について、インターネットで調べてみたり、
関連する職業の動画を一緒に見てみたり、
実際にその場所を訪れて見学する機会を設けるのも有効です。
例えば、ITに興味があればプログラミング体験、
動物が好きなら動物園やペットショップの裏側を
見学する機会を探すなど、
リアルな体験を通して興味を深めることができます。
インターンシップやボランティアなど、
短期間でも実際の職場で経験を積むことで、
自身の得意・不得意、そして向き不向きを
具体的に知る良い機会にもなります。
自己理解を深めるための対話:
お子さんが自身の特性を理解し、
「自分はこういう特性があるから、こういう環境だと力を発揮しやすいんだ」
と認識できるよう、対話を重ねましょう。
成功体験を振り返り、「どんな時にうまくいったか」
「その時、何が役に立ったか」を具体的に言語化することで、
自己肯定感を育み、自身の強みを認識する手助けになります。
苦手なことに対しても、「どうすれば対処できるか」
「どんなサポートがあれば楽になるか」を一緒に考えることで、
主体的に問題解決に取り組む姿勢を育みます。
2. 不登校のお子さんの場合
不登校のお子さんの進路選択では、「焦らないこと」と
「本人のペースを尊重すること」が何よりも大切です。
休養と心の回復を最優先に:
夏休みは、学校から離れて心身を休める絶好の機会です。
まずは、お子さんが安心して過ごせる環境を整え、
無理に学校へ行かせようとせず、
心の回復を最優先にしましょう。
家庭での穏やかな時間や、趣味に没頭できる時間を作ることで、
自己肯定感を少しずつ取り戻せるようサポートしてください。
学校以外の学びの選択肢を検討する:
必ずしも全日制高校への進学だけが選択肢ではありません。
通信制高校、フリースクール、高卒認定試験など、
様々な学びの場があります。
お子さんと一緒に、それぞれの選択肢について
情報収集をしてみましょう。
インターネットで調べたり、資料を取り寄せたり、
説明会に参加してみるのも良いでしょう。
「どんな場所なら安心して学べそうか?」
「どんな学び方なら続けられそうか?」という視点で、
お子さんの意見を尊重しながら検討を進めてください。
小さな成功体験を積み重ねる:
夏休み中に、何か一つでも「できた!」という成功体験を積むことが、
自信を取り戻すきっかけになります。

例えば、興味のある分野のオンライン講座を受けてみる、
ボランティア活動に参加してみる、習い事を始めてみるなど、
ハードルの低いことから始めてみましょう。
「〇〇をやってみない?」と誘う際は、
強制ではなく「もしよかったら、一緒にやってみない?」
と選択肢を提示する形で、お子さんの意思を尊重することが重要です。
対話を通じて自己肯定感を育む:
お子さんが自分の気持ちを
安心して話せる環境を作りましょう。
お子さんの話に耳を傾け、共感する姿勢を示すことで、
安心感を与えます。
「学校に行けないこと」にばかり焦点を当てるのではなく、
「〇〇ができるようになったね」「〇〇の才能があるね」といった、
お子さんの良い点や努力を具体的に褒めることで、
自己肯定感を高めていきましょう。
3. HSC(Highly Sensitive Child)のお子さんの場合
HSCのお子さんは、非常に感受性が豊かで、
周囲の環境や人の感情に敏感に反応します。
そのため、進路選択においても、
「安心できる環境」と「自身のペースで学べること」が重要になります。
五感を刺激する環境を避ける配慮:
HSCのお子さんは、光、音、匂い、
肌触りなどに人一倍敏感です。
オープンキャンパスや学校見学の際は、
人混みや騒音の多い時間帯を避けたり、
休憩をこまめに挟むなど、
お子さんの負担にならないような配慮をしましょう。
事前に学校の雰囲気や環境について情報収集し、
可能であれば、静かな時間帯に見学させてもらえるか確認することも有効です。
「得意なこと」や「興味のあること」を深掘りする:
HSCのお子さんは、深い思考力や共感力、
感受性の豊かさといった強みを持っています。
これらの特性を活かせる分野を見つけることが重要です。
夏休み中に、お子さんが心から楽しめること、
時間を忘れて没頭できることについて、
とことん深掘りする時間を作りましょう。
読書、芸術活動、自然観察など、
内面的な世界を豊かにする活動は、
HSCのお子さんにとって、将来の進路を考える上で
重要なヒントとなることがあります。
その「好き」が、将来どのような仕事や学びに
つながる可能性があるのか、親子で一緒に探求してみましょう。

自己肯定感を高めるサポート:
HSCのお子さんは、周囲の評価を気にしやすく、
自分を責めてしまう傾向があります。
「敏感であること」は弱点ではなく、
「豊かな感受性」という素晴らしい才能であることを繰り返し伝え、
自己肯定感を高めてあげましょう。
お子さんの感情を否定せず、「つらいね」「よく頑張っているね」と
共感的に受け止めることで、安心感が生まれ、
自信を持って進路を考えられるようになります。
《4. 不安障害のお子さんの場合》
不安障害を抱えるお子さんの進路選択では、
「スモールステップ」と「安心できるサポート体制」が鍵となります。
まずは「慣れる」ことから始める:
新しい環境や未知のことに対して強い不安を感じるため、
いきなり大きな目標を設定するのではなく、
小さな目標から段階的に慣れていくことを目指しましょう。
夏休み中に、気になる学校の資料を取り寄せてみる、
ウェブサイトを見てみる、
オンライン説明会に参加してみるなど、
まずは情報収集から始めてみましょう。
実際に学校を訪問する際は、短い時間から、
慣れた人と一緒に行くなど、お子さんのペースに合わせて
少しずつステップアップしてください。
安心できるサポート体制の確認:
進学先の学校に、カウンセリングルームがあるか、
スクールカウンセラーが常駐しているか、
通院中の医療機関との連携は可能かなど、
具体的なサポート体制について詳しく確認しましょう。
松陰高等学校のように、個別の相談に対応してくれる体制が
整っているかどうかも重要なポイントです。

保護者の方も自身の不安と向き合う:
お子さんの不安は、保護者の方にも伝播しやすいものです。
保護者の方が「大丈夫かな…」と不安を感じていると、
お子さんもさらに不安を募らせてしまう可能性があります。
保護者の方自身も、必要であれば専門機関に相談したり、
同じような悩みを抱える保護者の方と情報交換をするなどして、
自身の不安を軽減することも大切です。
お子さんに対しては、「きっと大丈夫だよ」
「一緒に考えていこうね」といった前向きなメッセージを伝え、
安心感を与えましょう。

《親子で乗り越える進路の壁:松陰高等学校が提供するサポート》
特性を持つお子さんの進路選択は、
決して簡単な道のりではありません。
しかし、適切なサポートがあれば、
お子さんは自分らしい未来を切り開くことができます。
松陰高等学校 高松校・丸亀校で
は、生徒さん一人ひとりの特性を理解し、
きめ細やかなサポートを提供することで、
それぞれの可能性を育んでいます。
1. 個別指導と学習サポート:自分のペースで学べる環境
松陰高等学校は広域通信制高校です。
つまり、全日制高校のように毎日学校に通う必要はありません。
これは、発達障がいや不登校、不安障がいなどで
集団生活や決まった時間割での学習に困難を感じるお子さんにとって、
大きなメリットとなります。
週に数回の登校でOK:
基本的には週に数回の登校で学習を進めます。
これにより、自分の体調やペースに合わせて
学習計画を立てることが可能です。
個別対応の学習指導:
一斉授業ではなく、生徒さん一人ひとりの理解度や
進捗に合わせた個別指導が中心です。
わからないことがあれば、すぐに質問できる環境が整っています。
タブレット学習の導入:
自宅での学習をサポートするため、
タブレットを活用した学習システムを導入しています。
これにより、場所を選ばずに学習を進めることができます。
視覚的な情報が得意な生徒さんや、
自宅で集中して学習したい生徒さんにとって有効なツールです。
得意を伸ばす多様な選択肢:
通常の高校科目だけでなく、興味や関心に合わせて
選択できる専門科目や体験学習も充実しています。
例えば、プログラミング、イラスト、
動画編集、資格取得支援など、
将来の夢につながる学びを見つけることができます。
2. きめ細やかなメンタルサポート
安心して学校生活を送るために:
特性を持つお子さんにとって、
心のケアは学習指導と同じくらい重要です。
松陰高等学校 高松校・丸亀校では、
生徒さんが安心して学校生活を送れるよう、
様々なメンタルサポートを提供しています。
担任教師との定期的な面談:
生徒さん一人ひとりに担任教師がつき、定期的に面談を行います。
学習の進捗だけでなく、日々の体調や悩み、困りごとなど、
どんな小さなことでも相談できる関係性を築くことを大切にしています。
専門カウンセラーによる相談体制:
専門カウンセラーが常駐または定期的に来校し、
生徒さんや保護者の方からの相談に応じています。
学校生活での悩み、友人関係、将来への不安など、
専門的な視点からアドバイスやサポートを提供します。
安心できる居場所づくり:
生徒さんがリラックスして過ごせる
フリースペースや休憩室を設けています。
無理に集団行動を促すのではなく、
自分のペースで過ごせる「居場所」があることで、
学校への安心感を高めます。
保護者の方へのサポート:
生徒さんの成長には、保護者の方の理解とサポートが不可欠です。
松陰高等学校では、保護者面談や情報提供、
セミナーなどを通じて、保護者の方が安心して
子育てや進路選択に取り組めるよう支援しています。

3. 進路指導:未来への扉を開くために
松陰高等学校では、生徒さんが自信を持って社会に羽ばたけるよう、
一人ひとりの特性や希望に合わせたきめ細やかな進路指導を行っています。
個別カウンセリングによる進路相談:
専門の進路指導担当者が、生徒さん一人ひとりの個性、
興味、得意分野、将来の夢などを丁寧にヒアリングし、
最適な進路を一緒に考えます。
大学、専門学校、就職など、多様な選択肢の中から、
お子さんに合った道を見つけるサポートをします。
体験学習や職場見学:
実際に社会と触れる機会を積極的に設けています。
職場見学、インターンシップ、職業体験などを通じて、
具体的な仕事内容や職場の雰囲気を肌で感じ、
将来のイメージを具体化することができます。
資格取得支援:
進路に役立つ資格取得をサポートしています。
検定対策講座や、資格取得のための学習支援などを行うことで、
生徒さんの自信と選択肢を広げます。
就職支援:
履歴書の書き方指導、面接練習、企業紹介など、
就職に向けた具体的なサポートも行っています。
特性を理解した上での企業選びや、
就職後の定着支援にも力を入れています。
夏休みに親子でできること:具体的なアクションプラン
夏休みは、進路について親子でじっくり話し合い、
情報収集をする絶好の機会です。
ここでは、具体的なアクションプランをご紹介します。
1 お子さんの「好き」と「得意」を見つけるワークショップ:
紙とペンを用意し、「好きなこと」「得意なこと」
「将来やってみたいこと」を書き出してみましょう。
お子さんの興味を引く写真や雑誌などを活用し、
視覚的にイメージを広げるのも良い方法です。
書き出したものをグループ分けしたり、
関連する職業を調べてみたりすることで、
新たな発見があるかもしれません。
2 学校説明会やオープンキャンパスへの参加検討:
松陰高等学校はもちろん、気になる学校があれば、
夏休み中に開催される学校説明会や
オープンキャンパスの情報を収集してみましょう。
オンラインでの説明会も増えているため、
自宅で気軽に情報収集することも可能です。
実際に足を運ぶ際は、お子さんの体調や特性に配慮し、
無理のない範囲で参加してください。
保護者向けのセミナーや相談会に参加:
特性を持つお子さんの進路に関する情報提供や、
専門家による相談会も多く開催されています。
情報収集だけでなく、同じ悩みを持つ保護者の方と
交流する機会にもなります。
3.図書館やインターネットでの情報収集:
進路に関する書籍を読んでみたり、
厚生労働省や文部科学省のウェブサイトで、
障がい者雇用や高等教育に関する情報を調べてみましょう。
松陰高等学校のウェブサイトもぜひご覧ください。
在校生の声や卒業生の進路、
学校生活の様子などが詳しく掲載されています。
「もしも」の未来を語り合う時間:
「もしも、〇〇になったら、どんな生活になると思う?」
「もしも、この学校に行ったら、どんなことができそう?」
具体的な未来像を親子で語り合うことで、
お子さんのモチベーションを高め、
具体的な目標設定につながります。
この際、お子さんの発言を否定せず、
「そうだね、それもいいね」と肯定的に受け止めることが重要です。

特性のある子の可能性を信じて:松陰高等学校からのメッセージ
特性を持つお子さんは、それぞれに素晴らしい個性と
無限の可能性を秘めています。
しかし、既存の教育システムの中では、
その特性が「苦手」として捉えられ、
本来持っている才能が見過ごされてしまうことも少なくありません。
松陰高等学校 高松校・丸亀校は、そうしたお子さんたちが、
「自分らしく」輝ける場所でありたいと願っています。
私たちは、発達障がい、不登校、HSC、不安障がいといった特性は、
決して「問題」ではなく、その子が持つ「ユニークな個性」
であると捉えています。
そして、その個性を尊重し、
それぞれに合った学びの場とサポートを提供することで、
お子さんたちが自信を持って社会へ羽ばたけるよう、全力で応援します。
この夏、親子でじっくりと進路について考え、
お子さんの「好き」や「得意」を再発見し、
未来への第一歩を踏み出すきっかけにしてください。
もし、「松陰高等学校についてもっと詳しく知りたい」
「うちの子のケースでも大丈夫だろうか」
といった疑問や不安をお持ちになったら、
どうぞお気軽にご連絡ください。
私たちは、皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
お子さんの可能性を信じて、
一緒に最善の進路を見つけていきましょう。
《最後に…》
松陰高等学校 高松校・丸亀校では
WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査や
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査の結果を元に
お子さんにとっての
ベストな教育環境や指導方針を組み立てています。
また、ご希望の方は、松陰高等学校 高松校・丸亀校でも
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査を実施しています。
どんな子どもでも
さまざまな特性があります。
その特性は
子どもを苦しめるだけではなく
使い方を変えれば
大きな武器になるのです。
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査をもっと活かしたい方は
いつでもお気軽にご連絡ください。
お待ちしております。
また、WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査や
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査を
ご自身でとれるようになりたい先生は
WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査のとり方や
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査のとり方も
お教えしています。
その場合もお気軽にお問い合せください。
では。。。
松陰高等学校 高松校・丸亀校
☎087-813-3781
✉info@kagawa-mirai.jp