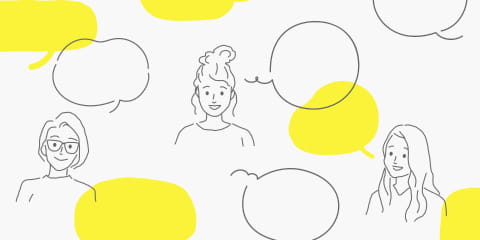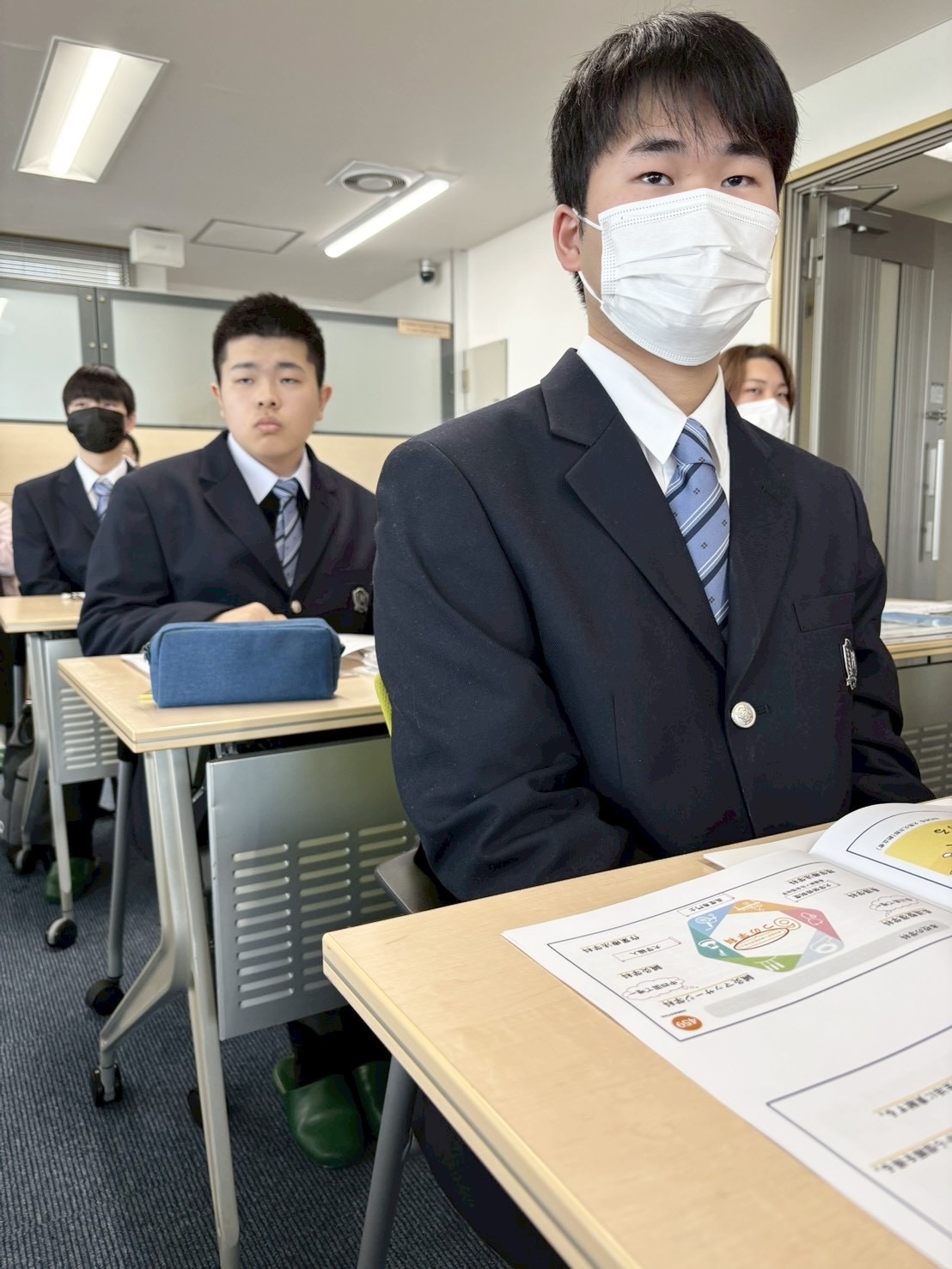心理士カウンセラーのブログ
Psychological counselor Weblog
【高校選びの迷路から脱出!WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査を「道しるべ」にする方法】
2025.04.27
長年、多くの子どもたちや保護者の方々と向き合う中で、
避けては通れない大きな壁の一つが
「高校選び」だと痛感しています。
中学3年生になり、
将来を見据えた進路選択の時期が近づくと、
お子さんだけでなく、保護者の皆様も
深い「迷路」に迷い込んだような感覚に陥ることがあります。
「どこの高校が良いのだろう?」
「この学力で入れる学校は?」
「将来、何をしたいのか分からない」
「子どもに合う学校ってどんなところ?」
このようにさまざまな情報が錯綜し、
偏差値という分かりやすい指標に
振り回されそうになる中で、
お子さんにとって本当に最善の選択をすることの
難しさを感じていらっしゃるのではないでしょうか。
この複雑で先の見えない迷路を、
少しでも安心して進むための「道しるべ」となりうるツールとして、
今回は「WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査」をご紹介し、
その活用法について詳しくお話ししたいと思います。
《なぜ高校選びは「迷路」なのか?》

かつてに比べて高校の多様性は増しました。
全日制、定時制、通信制、普通科、
専門学科(工業、商業、農業、水産、家庭、看護、情報、福祉など)、
総合学科、単位制、学年制、
私立、公立、国立…
選択肢は豊富になった一方で、
それぞれの特色や雰囲気を理解し、
お子さんの個性や能力、興味関心、価値観
と照らし合わせる作業は、膨大な時間と労力を要します。
さらに、近年では大学入試改革の影響もあり、
「どのような学びをしたいか」
「将来どうなりたいか」といった、
より内面的な問いに向き合う必要性が高まっています。
偏差値だけで輪切りにできるほど、
人の成長や可能性は単純ではありません。
お子さん自身の「好き」「得意」「苦手」といった感覚や、
どのような環境であれば最も力を発揮できるのかを見極めることが、
後々の満足度や成長に大きく関わってくるのです。
しかし、中学生という多感な時期に、
自分自身のことを客観的に理解し、
将来像を具体的に描くことは容易ではありません。
保護者の方も、お子さんの見えやすい側面
(テストの点数や授業態度など)で判断しがちですが、
お子さんの持つ潜在的な能力や認知特性といった、
目には見えにくい部分を理解することは、
より適切な「道」を選ぶ上で非常に重要になります。
《WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査とは?》
ここで登場するのが、WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査です。
正式名称は「ウェクスラー式 児童用 知能評価尺度 第5版」といい、
主に5歳0ヶ月から16歳11ヶ月の子どもを対象とした、
世界的に最も広く使われている代表的な「知能検査」です。
「知能検査」と聞くと、「IQ(知能指数)を測るもの」
というイメージが強いかもしれません。
確かにIQも算出されますが、
WISC-Ⅴ検査の真価は、
単一のIQスコアだけにあるのではありません。
この検査は、子どもの様々な認知能力を多角的に測定し、
その結果を「認知の偏り」や「得意なこと・苦手なこと」
として理解するための非常に有用なツールなのです。
WISC-Ⅴ検査は、主に以下のような5つの領域
(主要指標)の能力を測定します。
◎言語理解指標(VCI: Verbal Comprehension Index):
言葉の知識や概念の理解、言葉を使った推論能力などを測ります。
語彙力、言語による抽象的な思考力、聞き取った情報を理解する力などに関わります。
◎視空間指標(VSI: Visual Spatial Index):
目で見た情報を理解し、空間的な操作を行う能力を測ります。
図形やパズルを組み立てる能力、地図を理解する能力、
視覚的なイメージを操作する能力などに関わります。
◎流動性推理指標(FRI: Fluid Reasoning Index):
新しい問題に対して、これまでの知識や経験に頼らず、
論理的に推論して解決する能力を測ります。法則を見つけ出す力、
抽象的な問題を解決する力などに関わります。
◎ワーキングメモリ指標(WMI: Working Memory Index):
一時的に情報を心の中に保持し、それを操作・処理する能力を測ります。
「頭の中のメモ帳」や「情報処理の作業台」に例えられます。
指示を覚えながら作業を進める力、計算の途中の数を覚えておく力などに関わります。
◎処理速度指標(PSI: Processing Speed Index):
簡単な視覚情報を素早く正確に処理する能力を測ります。
目で見た情報を素早く認識し、反応する力などに関わります。
ノートを取る速度、問題を解く速度などに関わることがあります。
これらの主要指標の他に、より詳細な能力を見るための
補助指標もいくつか用意されています。
WISC-Ⅴ検査は、訓練を受けた心理士によって
1対1で実施されます。
さまざまな課題(質問に答える、図形を組み立てる、
数を記憶する、記号を書き写すなど)を通して、
お子さんの認知能力のプロフィールが明らかになります。
《WISC-Ⅴ検査の結果を「道しるべ」にする方法》

では、このWISC-Ⅴ検査の結果を、
どのように高校選びの「道しるべ」として活用できるのでしょうか?
単に「IQが高いから進学校」「低いから職業訓練校」
といった単純な話では決してありません。
重要なのは、5つの主要指標や補助指標のバランス、
つまり「認知のプロフィール」を理解し、
それがどのような学び方や環境に適しているかを考えることです。
以下に、具体的な活用のヒントをいくつかご紹介します。
◎得意な能力を活かせる環境を探す:
・言語理解指標(VCI)が高い:
読解力や文章理解、議論などが得意な可能性があります。人文科学系や社会科学系に力を入れている高校、授業でディスカッションやプレゼンテーションが多い学校などが合っているかもしれません。
・視空間指標(VSI)が高い:
図形や空間を捉えること、視覚的な情報処理が得意な可能性があります。美術、デザイン、建築、工学、理学といった分野に強い専門学科や、実験・実習が多い理数系の学科などが魅力的に映るかもしれません。
・流動性推理指標(FRI)が高い:
新しい問題解決や論理的な思考が得意な可能性があります。探究学習に力を入れている高校、STEAM教育(科学、技術、工学、芸術、数学を横断的に学ぶ分野)を取り入れている学校など、自分で考えて課題を解決していくスタイルの学びが多い環境が刺激的かもしれません。
・ワーキングメモリ指標(WMI)が高い:
複雑な指示を理解し、複数の情報を同時に処理することが得意な可能性があります。情報量の多い講義形式の授業や、多くの課題を並行して進めるような環境でも対応しやすいかもしれません。
・処理速度指標(PSI)が高い:
情報を素早く処理し、テキパキと作業をこなすことが得意な可能性があります。大量の情報を扱う事務系の学科や、スピードが求められる作業が多い環境などで力を発揮しやすいかもしれません。
◎苦手な能力に対してサポートがあるかを確認する:
もし特定の指標が他の指標に比べて著しく低い場合、
その能力を使う場面で困難を感じやすい可能性があります。
例えば、ワーキングメモリが低い場合、
長い指示を覚えたり、
板書を写しながら先生の話を聞いたりするのが
難しく感じるかもしれません。
処理速度が遅い場合、
テストの時間内に問題を解ききれなかったり、
ノートを取るのに時間がかかったりするかもしれません。
このような認知の特性を理解した上で、
「ノートテイキングのサポートがあるか」
「情報保障(視覚情報だけでなく音声情報も提供するなど)が手厚いか」
「個別の進度に対応してくれるか」「補習や質問しやすい環境があるか」など、
学校側のサポート体制を確認することが重要です。
必ずしも特別な支援クラスがある必要はありませんが、
先生が生徒一人ひとりの特性を理解しようと努めているか、
相談しやすい雰囲気があるかといった点も、大きな「道しるべ」になります。
◎学習スタイルとの相性を考える:
WISC-Ⅴ検査の結果は、その子がどのような方法で情報をインプットし、
処理するのが得意かを示唆します。
例えば、視空間指標が高い子には図やグラフ、
映像を使った説明が分かりやすいかもしれません。
言語理解指標が高い子には、
言葉での説明や読書が効果的かもしれません。
学校の授業形式はさまざまです。
講義中心なのか、グループワークが多いのか、
実験・実習が多いのか、ICTを活用しているかなど、
学校の学習スタイルがお子さんの認知特性と
合っているかを検討する際に、
WISC-Ⅴ検査の結果は役立つ視点を提供してくれます。
◎無理のないペースで学べる環境を選ぶ:
特にワーキングメモリや処理速度の指標が低い場合、
情報のインプットや処理に時間がかかる傾向があります。
授業の進度が速すぎる学校や、
課題の量が非常に多い学校では、
ついていくのが難しく、
自己肯定感を損なってしまう可能性があります。
お子さんの認知特性に合った、
無理のないペースで学べる学校を選ぶことは、
長期的な学習意欲を保つ上で非常に重要です。
少人数制のクラス、きめ細やかな指導、
繰り返しの学習を重視するスタイルなどが適している場合もあります。
◎自己理解を深め、自信を持つための材料にする:
WISC-Ⅴ検査の結果は、お子さん自身の
「取扱説明書」のようなものです。
単なる優劣ではなく、
「自分はこういう情報の処理の仕方が得意なんだな」
「こういうところは少し苦手だから、こう工夫してみよう」といった、
客観的な自己理解を深めるための貴重な機会となります。
特に、特定の分野で苦手意識を持っているお子さんの場合、
それが能力の偏りによるものであることが分かると、
「努力が足りないわけではなく、
やり方が合っていなかっただけなんだ」と気づき、
自分を責める気持ちが和らぐことがあります。
得意な部分に目を向けることで、
失いかけていた自信を取り戻すきっかけにもなり得ます。
《WISC-Ⅴ検査の結果を最大限に活かすために》

WISC-Ⅴ検査の結果は、
それ単独で進路を決めるものではありません。
あくまで「道しるべ」の一つです。
結果を最大限に活かすためには、
いくつかの重要なステップがあります。
1)専門家による丁寧なフィードバックを受ける:
WISC-Ⅴの検査結果は数値だけでなく、
検査中の行動観察なども含めて総合的に解釈される必要があります。
必ず検査を実施した臨床心理士や公認心理師から、
お子さんの特性や結果の持つ意味について、
分かりやすく丁寧な説明を受けてください。疑問点があれば遠慮なく質問しましょう。
2)結果をお子さんと共有する(年齢に応じて):
検査結果を、お子さんにも分かりやすい言葉で伝えましょう。
「あなたはこれが得意なんだね」
「こういう時は少し時間がかかるみたいだけど、
こういう工夫をすれば大丈夫だよ」
といったように、前向きで建設的なメッセージとして
伝えることが大切です。
決してネガティブなレッテル貼りにならないように
注意が必要です。
お子さん自身が自分の特性を理解し、受け入れることが、
今後の成長にとって非常に重要になります。
3)検査結果を他の情報と組み合わせる:
WISC-Ⅴ検査の結果は、お子さんの
「認知能力」の一側面を示したものです。
これに加えて、これまでの学習の記録(成績、模試の結果)、
学校での様子(授業への取り組み方、
友達との関わり、部活動など)、お子さんの興味関心、
将来の夢や希望、価値観、そして何よりもお子さん自身の
「行きたい」という気持ちを総合的に考慮して、
進路を検討する必要があります。
4)学校見学や説明会に足を運ぶ:
気になる高校があれば、
必ず学校見学や説明会に参加しましょう。
学校の雰囲気、先生と生徒の関わり、
施設の状況、授業の様子などを肌で感じることが、
その学校がお子さんに合っているかを
見極める上で非常に役立ちます。
可能であれば、先生に進路相談をしたり、
お子さんの特性について伝えたりする機会を持つのも良いでしょう。
5)焦らず、お子さんのペースで検討する:
高校選びは人生の大きな選択の一つですが、
一度決めたら変更できないわけではありません。
また、入学後に新たな興味が湧いたり、
考え方が変わったりすることもあります。
お子さんの成長は続いていきます。
完璧な答えを一度で見つけようと気負いすぎず、
お子さんとじっくり話し合いながら、
納得のいく選択を目指しましょう。
《WISC-Ⅴ検査が「万能の答え」ではないこと》
強調しておきたいのは、WISC-Ⅴ検査が
高校選びの「万能の答え」を提供するものではないということです。
人の可能性は、数値や検査結果だけで
測れるものではありません。
検査で測れる認知能力は、
その子を構成する要素のごく一部に過ぎません。
お子さんの「やる気」「興味・関心」
「好きなこと」「粘り強さ」「コミュニケーション能力」
「創造性」「リーダーシップ」といった、
数値化しにくい大切な側面は、
WISC-Ⅴ検査だけでは分かりません。
これらの要素こそが、高校生活やその後の人生を
豊かにする上で、非常に重要な意味を持つのです。
WISC-Ⅴ検査は、あくまで
お子さんの認知特性を客観的に理解するための
一つの「手がかり」であり、
複雑な高校選びの迷路を照らす「道しるべ」です。
この道しるべを頼りに、
お子さん自身の内なる声に耳を傾け、
保護者の方との対話を重ね、
さまざまな情報を丁寧に吟味することで、
きっとお子さんに最適な「道」を見つけることができるはずです。
高校選びは、お子さんがこれからの人生を
どのように歩んでいくかを考える、大切な通過点です。
迷うのは自然なことであり、
決して恥ずかしいことではありません。
むしろ、それだけ真剣にお子さんの将来を考えていらっしゃる証拠です。
もし、高校選びで行き詰まりを感じていたり、
お子さんの特性についてもっと深く理解したいと思ったりしたら、
WISC-Ⅴ検査を受けてみることを検討してみてください。
そして、その結果を専門家と一緒に丁寧に読み解き、
お子さん自身の声に耳を傾けながら、
この「迷路」を乗り越えるための「道しるべ」として活用していただければ幸いです。
お子さんにとって、希望に満ちた高校生活が送れるよう、
心から応援しています。
何かご心配なことや、さらに詳しく知りたいことがあれば、
松陰高等学校 高松校・丸亀校に相談してください。
皆様の「道しるべ」探しをサポートしてくれるでしょう。
また、このブログが、高校選びという「迷路」の中で
立ち止まっている皆様にとって、一筋の光となることを願っています。
松陰高等学校はWISC‑Ⅴ検査を羅針盤に、
お子さまの“強みが光る学び方”を
一緒にデザインします。
まずは、個別相談や説明会へ
お気軽にお越しください。
発達障害があっても
中学時代に不登校だったとしても、
未来は選べます。
WISC‑Ⅴ検査で理由を解き明かし、
“行ける学校”ではなく
“行きたくなる学校”で新しい一歩を踏み出しましょう。
《最後に…》
松陰高等学校 高松校・丸亀校では
WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査や
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査の結果を元に
お子さんにとっての
ベストな教育環境や指導方針を組み立てています。
また、ご希望の方は、松陰高等学校 高松校・丸亀校でも
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査を実施しています。
どんな子どもでも
さまざまな特性があります。
その特性は
子どもを苦しめるだけではなく
使い方を変えれば
大きな武器になるのです。
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査をもっと活かしたい方は
いつでもお気軽にご連絡ください。
お待ちしております。
また、WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査や
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査を
ご自身でとれるようになりたい先生は
WISC-Ⅴ(ウィスク5)検査のとり方や
WISC-Ⅳ(ウィスク4)検査のとり方も
お教えしています。
その場合もお気軽にお問い合せください。
では。。。
松陰高等学校 高松校・丸亀校
☎087-813-3781
✉info@kagawa-mirai.jp